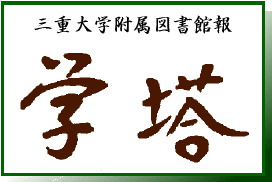
目次
- サービスの改善と展開を図ります
−就任にあたって− 柴田正美 - 図書館の思い出
−四季を感じる図書館 伊藤 敏子 - 21世紀に翔ばたく三重大学生諸君へ
読書の勧め 駒井 喬 - 寄贈図書
- 主要日誌
- 100号を祝う 柴田 正美
No.100 1998.11.11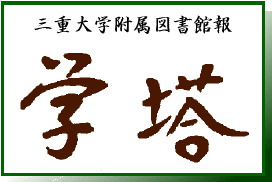 |
目次
|
![]()
中田常男先生の後を引き継いで就任いたしました。人文学部でおこなっております教育・研究領域と非常に近い関係の職務であり,理論と実践の統合的把握を進めなければならない立場と考えて,職務に専念する所存です。
さて,附属図書館の抱えている課題は数多くあります。なかでも早急に対応すべきものは、地域への貢献と学生に対するサービスの展開でしょう。「地域への貢献」の形態としては,地域住民の直接利用を推進するものと,地域に所在する公共図書館等の組織・機関を仲介して提供するサービスとがあります。附属図書館に来館して資料・情報を利用する地域住民は,これまでも多くの例がありましたが,資料の貸出という利用形態はあまり重視されてきませんでした。大学図書館の使命が大学における教育と研究を第一とするという理由から,短期間とは言え,コントロールの難しくなる事態を避けようとの判断によるものでした。けれども,大学が地域において期待されている姿を考えるとき,方針を改める必要が感じられます。手始めに,大学あるいは各学部等が開催する「公開講座の受講生に,受講年度に限って資料の貸出を認める措置を取ることとしました。公開講座は,その多くが学問研究への入り口・ガイド的機能を果たすことを考えると,それを契機としてより深く学習・研究を進めたいと思う地域住民が多くなって当然でしょう。この人たちに資料・情報を提供する責任を附属図書館は担う
ことが求められます。公共図書館等の組織・機関を仲介とするサービスの提供は,従来から追及されてきたところです。1993年11月に発行されている『三重県図書館雑誌新聞総合目録』第1版も一つの具体例といえるでしょう。三重県立図書館をセンター館として形成されつつある「三重県図書館ネットワーク」にも構想の策定段階から附属図書館は参画し,文部省の管轄する学術情報センターとのネットワーク形成・構築・運営等の経験を積極的に反映させてきています。これらの協力関係が深まる中で,今後とも、地域住民へのサービスは拡大・深化が図られることとなります。
つぎに,学生に対するサービスの展開です。学生部の発行する『学園だより』第146号の部局たよりで紹介しておきましたが、平成9年度の自己点検・評価報告書で、かなり立ち入った調査とその結果を明らかにしています。
そこでは、学生用図書購入費の絶対的な少なさと、少ないものが必ずしも効果的に蔵書構成の充実に反映されていない実情を認識しています。自己点検・評価は、その結果にもとづいて新たな方向性を打ち出し、その実現に向けて努力してこそ意義のあるものとなるでしょう。
就任以来、こうした実情を変えるべくいくつかの方策を試みています。各学部および共通教育機構から推薦を受けて購入する「基礎的専門図書」としての「学生用図書」に授業等の概要を示しているシラバス掲載の資料を積極的に推薦いただくようお願いしました。授業に直接関わりのある資料が、附属図書館に所蔵されていないという事態の改善を始めています。次には、授業に直接関わりの無い、あるいは、最近の学界動向を反映した基礎的専門図書も多く刊行されていますので、こうした資料の収集を徹底する必要があると考えています。もともと少ない学生用図書のための資料購入費ですから、一度に全部の分野を充実することは難しいと思いますので、各年においては分野を限定しながらも、数年間を合わせて見ると充実への方向性が見出せるような形の実現を目指しています。
附属図書館が、「学習図書館」としての機能だけを追及していたのでは、多くの学生諸君からのサポートを受けることができないでしょう。学生生活全般において「役に立つ」ことをアピールできる力を備えるべきだと考えています。そうした試みとして、附属図書館2階の雑誌コーナーの改装と充実があります。書架の配置のまずさから見落とされることの多かった雑誌コーナーを分かりやすくすること、雑誌のもっている「情報の新しさ」を訴えること、くつろいだ雰囲気で利用できるようにすること、備え付けている雑誌の種類を再検討し、人気のある・読まれそうな・「新しさ」に注目されるようなものを展示すること、学内のニュースを容易に入手できるコーナーを目指すこと、などを念頭に置きながら改装と充実を図りました。
教官の期待している「研究図書館としての機能」を高めるために、学術情報サービスの提供を高度化できるような事務組織の変更も行いました。さらにCD-ROMサーバーを導入し、情報検索サービスの多様化に着手します。話題の「電子図書館」を目指す試みも始めたいところです。
これまで少しずつ貯めてきた力を多くの方面で一気に展開できるような環境がやっとのことで整ったと考えてください。
けれども、建物は古く手狭です。実現できるようになった学術情報サービスを十全に利用できるようにする情報機器の配置場所も機材も恵まれていません。サービスを基本的に支える図書館職員の人数も十分とはいえない状況です。これらの課題の解決のためには、各位のご理解とご支援がなければ困難です。私たちは、サービスの改善と展開が各位のご理解とご支援の元になるとの考え方で臨んでいくつもりです。
2階雑誌コーナーにあらたに置かれる雑誌
|
|
 |
教育学部助教授 伊藤敏子
 振り返ってみると図書館とのつきあいは長い。図書館で頻繁に本を借りた記憶はあまりよみがえってこないが、図書館で感じた四季の記憶は今も鮮やかだ。大学進学までの18年間を過ごした愛媛の田舎町には、「温芳図書館」という町立の図書館があった。まだ字の読めなかったころ、母が小説を借りるとき、兄が童話を借りるとき、私は一緒にそこにでかけてその名前のとおり古めかしくどこか懐かしいその図書館の雰囲気を愉しんだ。入口近くのわずかばかりの小説本と童話本の背後には、ほとんど借りられることのない旧仮名遣いの本が古書独特の香りを発散させながら広い空間を占領していた。日常性から遊離した不思議な風景を前に、私の胸の鼓動は高まった。重い木製の窓枠の向こうは日常の世界。しかし、息のつまるような暑い夏の日に、きっちりと高い天井まで作り付けた本棚に囲まれたその空間だけはひんやりとし、耳たぶの真っ赤になるような寒い冬の日に、古びた背表紙のならぶ本棚は気のせいかほっこりと暖かかった。字が読めるようになってからも、本を借りるためではな
く、嫌なことがあったとき、一人になりたいとき、この非日常性の空間で憩うため、よく図書館に出かけた。高等学校進学のころ、明治の近代建築を思わせるこの石造りの図書館は取り壊され、同じ場所に真っ白な冷暖房完備の図書館が建てられた。静かで秘密めいた図書館は姿を消し、賑やかで明るい図書館が生まれた。誰からも借りられることのなかった古い図書は一掃され、本棚は梯子なしで最上段に手が届く便利なものになり、図書館は日常性のなかへと融け込んでいった。そして、私の足はなんとなくこの図書館から遠のいた。
振り返ってみると図書館とのつきあいは長い。図書館で頻繁に本を借りた記憶はあまりよみがえってこないが、図書館で感じた四季の記憶は今も鮮やかだ。大学進学までの18年間を過ごした愛媛の田舎町には、「温芳図書館」という町立の図書館があった。まだ字の読めなかったころ、母が小説を借りるとき、兄が童話を借りるとき、私は一緒にそこにでかけてその名前のとおり古めかしくどこか懐かしいその図書館の雰囲気を愉しんだ。入口近くのわずかばかりの小説本と童話本の背後には、ほとんど借りられることのない旧仮名遣いの本が古書独特の香りを発散させながら広い空間を占領していた。日常性から遊離した不思議な風景を前に、私の胸の鼓動は高まった。重い木製の窓枠の向こうは日常の世界。しかし、息のつまるような暑い夏の日に、きっちりと高い天井まで作り付けた本棚に囲まれたその空間だけはひんやりとし、耳たぶの真っ赤になるような寒い冬の日に、古びた背表紙のならぶ本棚は気のせいかほっこりと暖かかった。字が読めるようになってからも、本を借りるためではな
く、嫌なことがあったとき、一人になりたいとき、この非日常性の空間で憩うため、よく図書館に出かけた。高等学校進学のころ、明治の近代建築を思わせるこの石造りの図書館は取り壊され、同じ場所に真っ白な冷暖房完備の図書館が建てられた。静かで秘密めいた図書館は姿を消し、賑やかで明るい図書館が生まれた。誰からも借りられることのなかった古い図書は一掃され、本棚は梯子なしで最上段に手が届く便利なものになり、図書館は日常性のなかへと融け込んでいった。そして、私の足はなんとなくこの図書館から遠のいた。
代わって私を非日常性への旅に誘ったのは、「養正の丘」と呼ばれる小高い丘の上に建つ高等学校の附属図書館だった。丘の下に広がる平野は稲作地帯で、春には苗代で水を張られた平野が空を映して鏡のようにひかり、夏にはその平野が緑にそよぎ、秋にはその平野が黄金色にそまった。その背後には数多の小島を浮かべた瀬戸内海が青く輝き、天気のいい日には水平線がくっきりと見えた。高等学校の附属図書館は、この風景を臨む方向を採光のよいガラス張りにして校舎の離れに建てられていた。日常性から距離をとりたくなると、私はそこで季節ごとに変わる風景をまえに詩や小説のようなものをつくっていた。物理的にそこで過ごした時間はわずかであったかもしれないが、多感な年齢であったせいか、心のどこかでまだ息づいている。
大学修士をおえて、私はスイスの首都ベルンに留学した。大講義室での講義は大学本館で行われるが、その本館の最上階には法学部図書館があった。一日に複数の講義のある日、私はこの図書館で空き時間を過ごすことが多かった。キャンパスに色とりどりの花の咲き乱れる春、すりガラスごしに見るように街並みが霧に沈む秋、凍てつくような青い空の下にアルプスの山々が迫ってくる冬。アルプスの輪郭の大小は、アルプスからの距離の遠近ではなく、見る視角の広狭によるという原則を得たのもこの図書館だった。図書館の窓際で、セミナーやコロキウムの発表を前に一秒を惜しんで手持ちの本を読むこともあったが、たいていは眼前に広がる世界にあれこれととりとめのない思いを馳せて空き時間は過ぎていった。故郷を遠く離れた街で思いを馳せる対象がつきることはなかった。
講義のないときには学科図書館、国立図書館、市立図書館、地域図書館に出かけた。学科図書館はもちろん専門書・専門雑誌の宝庫である。線を引きながら読まないとあまり頭に残らない性分の私は、夕刻のあるいは休暇中のこの図書館でしばしばコピー機と格闘した。ちょうど目の高さにある窓からの風を感じながら、遠景にある古めかしい邸宅とその邸宅を包む広葉樹の木立に視線を定めて、その葉の色合いの変化にときには心をおどらせ、ときには感傷的になりながら、このコピー作業の習慣は5年間にわたって断続的に続いた。国立図書館ではスイスで出版された図書およびスイスに関する図書がそろっていて、ペスタロッチー研究をしていた私には重力源になるような図書館だった。ペスタロッチーの著作はもちろんのこと、ペスタロッチーをテーマにしたさまざまな時代のさまざまな言語の著作も――スイスが戦災に遭っていないことも幸いしているが――ここでは確実に閲覧できる。各国の大使館が並ぶ緑深い地域に位置するこの図書館の窓からも、四季の移ろいはあますところなく流れ込んでくる。ヨーロッパの真ん中でヨーロッパらしからぬ意見を主張し続けてきた小国スイスの長い歴史を
蔵した図書館が、異文化の集中する地域の一角にどっしりと腰をおろしている偶然を思うと、四季の移り変わりもなんとなく厳かで愛しいものに感じられる。市立図書館は分野と言語を問わずもっとも広範に図書を閲覧できる図書館である。この図書館では、当該図書館にない図書をスイス国内の他図書館から80円で、スイス国外の他図書館から240円で取り寄せてもらうことができ、このシステムを介してほとんどの必要図書は手に入れることができた。旧市街の中心に位置したこの図書館では、噴水のある中庭に設置されたガーデン・チェアで本を読むこともできるし、そこから2分も歩けばベルン旧市街を包み込むようにして流れているアーレの河畔に出て本を読むこともできる。天気がいい日にはアルプスを一望できるこの河畔で、水鳥や草木とたわむれているあいだに自然は季節とともに移ろっていった。地域図書館へは新聞・雑誌・童話を読むためによく足を運んだ。この図書館では、「推薦図書」に陳列された図書のテーマで、また集まった子どもたちの様子で、季節の変遷が実感された。クリスマスに、夏休みに、それぞれのテーマでならべられた図書とそこに集まる子どもたちの表情をみて
いると、新しい季節の訪れに文化圏を異にする私の心もおどった。
日常生活がとても不幸に思えた10代のころ、異郷の日常生活にときおり沈むことのあった20代のころ、私の居場所はいつも図書館にあった気がする。「子どもの居場所」が論議される昨今、学校の保健室も地域社会の人間ももちろん大切だが、少しだけ違った目で図書館を見れば子どもはもちろんかつて子どもだった人もそこにもう一つの居場所をみつけられるかもしれない。読書の勧めならぬ、図書館の勧めの提言。
戦後50年を経て、政治から金融、経済、産業の在り方はたまた教育改革まで様々な、国、地方を含めた、社会のシスティムの改革が声高らかに叫ばれている今日この頃です。戦後、最も爛熟した時代に生まれ、育ち、現在、三重大学に在学中の諸君には、余り差し迫った話として捉えられていないと思われますが、現実には、産業界の不況から来る新卒就職戦線の締め付けなど、じわじわと君たちの実力が試される、自由でオープンな競争社会が目前に迫っています。ここ20数年の間、大学での教育は、ある一定の基準の専門技術を修得した学生を、なるだけ多数、産業界に供給することに目的をおいていたように思われます。従って、中学、高校時代から、より格上の大学へ入学するために目的を絞った勉強法一筋で、大学へ入っても、単位の収得を第一義とした受験勉強式理解法によって進学し、卒業資格まで得ようとする連中が大半を占めるようになっているようです。
元々わが国の教育制度は維新の頃から「列強に追い付け」「列強に真似ろ」といった御題目で整備されてきたものと思われるが、古くは旧制高校、大学予科で、ヨーロッパの大学教育の伝統に根ざした、語学、数学、自然科学、哲学など、一般教養教育をしっかりやってから大学における専門教育へという伝統が培われ、我々の年代でも大学入学後、教養部で1年半一般教養教育をしっかりとやってから、その成績により希望進学学部、学科が決まったものである。1960年代から70年代にかけての日米安保闘争の時代に、教養教育課程では、社会と個人、社会と大学、民主主義とはに始まり政治、経済、科学、学問の本質に至まで活発な議論がなされたものである。所謂、リベラルアーツは日本にもまともに定着するかに見えたが、70年代に至り、一部学生グループの尖鋭化、過激化、政治問題化に伴い、一般教育課程が大学教育のシスティムから疎んぜられるようになる。三重大学でもこの程ようやく一般教育の改革が年度進行と共に終了したと聞く。
そもそも大学における教育は、「判らないことを実験事実と理論を論理的に結び付けて判るようにする」「だれもやったことがない新しい物質間の関係を発見する」といった積極的で前向きな学習を支持し、助けることをモットーとする。学生にとって人とは違う自己の確立、自分の天性の発見、プロとして大人の世界に打って出る覚悟を決めるなど、自分で自分を鍛える学習が求められる。このような大学本来の教育に対する、リベラルアーツ或いは一般教養教育のはたす役割は現在ますます多大となっていると考えられるが、社会の要請とは時代軸的にフェイズが完全に逆転している現状では、学生諸君はこれを自学自習で乗り切るほかに手が無くなっている。
日本独特の縦割りの社会の中で、日本独特の文化、文明に立脚した社会、組織、個人に関して、司馬遼太郎の著作から「菜の花の冲」「翔ぶが如く」「戦雲の夢」などを読んで、また、キリスト教の理念を背景とした、自由、平等、博愛の精神に立脚した民主主義を基に書かれたアーサー・ヘイリーの著作「ストロング・メディシン」「最後の診断」などから国、社会、組織と個人、社会正義と個人、義務と責任等を学んで欲しい。さらに、一見、通俗活劇調ではあるが、爛熟した大英帝国の遺産を受け継ぐ貴族社会出身の政治家と貧しい階級の生まれながら崇高な政治倫理と哲学を持つ政治家の次元の高い闘争を描いたジェフリー・アーチャーの著作「めざせダウニング街10番地」やイギリスのインテリ層のウイットとエスプリに富んだゲーム感覚の活劇から「百万ドルを取り返せ」を読んで、大英帝国の遺産を引き継ぐ英国紳士の文化に触れて欲しいと思うものである。特に文字、文を読むことより、その記述を論理的に組み立て自分自身のイメージをつくるという作業を繰り返して、大人としての自分の人間性の基準をどこに置くか考えてみて欲しいものです。
附属図書館長 柴田 正美
『学塔』の創刊号が出されたのは昭和48年(1973)8月のことであった。その最初のページのレイアウトは現在のものと似ているが、タイトルが入っていない。記事の中で「タイトル募集中」と示されており、タイトルも決めないままで、今風に表現すれば「なにはともあれ、情報の発信をしよう」ということで創刊されたようである。
爾来25年、ここに100号をめでたく迎えることができた。途中に「新図書館建設」と「利用規程の全面改正」をテーマとする号外が都合3回出されている。ご執筆いただいた人が延べ236人、2度・3度のご登場をお願いした人も多く、実数では185人となる。ご執筆いただいた方々をはじめ、100号に至る歴史を支えていただいた多くの方に改めて御礼申し上げる。
本来は非常に私的なものであり文章には表現しにくい読書体験を積極的にご披瀝された方、図書館の有用性を海外での経験を交えて語っていただいた方、大学図書館のあるべき姿や今後の展開方向について期待を述べた方、私たちのいたらなさを言葉優しく叱責してくれた方、多くの書物のもつ魅力と魔力を巧みに説き明かした文章、等々。100号を繙くと多彩である。中でも面白く読ませていただいたのが、学問領域の最先端の知識を反映しながら、資料や図書館がそれらの展開に役立つ状況を述べられたものである。と同時に身の引き締まる思いもした。
「図書館報」が担うべき機能としては、図書館の動きや展開方向について周知すること、上手な利用者を育てるための案内(毎年刊行してきた「新入生特集」号がこれにあたる。)、図書館の役割を利用者である教官に語っていただくこと、書評という形での資料の紹介、などがある。これらの機能の中で最も重視すべきものは、図書館の役割・果たすべき姿を描いていただくことであろう。第30号前後までは「利用者の声」という形のものもあった。一方通行でない『学塔』をつくる過程で、附属図書館のあるべき姿を共有したいと考えている。