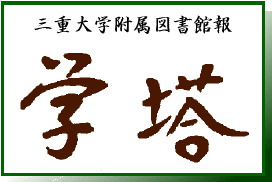
目次
- 無題・・・櫻井 實
- 津藩の修史事業・・・藤田 達生
- 「百部叢書集成」について・・・道坂 昭廣
- 寄贈図書
- 主要日誌
- 図書館からのお知らせ
No.102 1999.3.30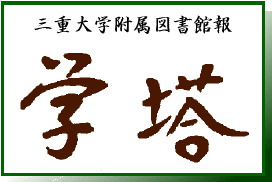 |
目次
|
![]()
専門書を含めて、本を読む機会が年々少なくなるが、たまたま今年は、2冊の良書に遭遇できた。
やはり良書を読んだ後の、すがすがしい気分は、たとえようもなく良い。ここに推薦する本は、いずれも200頁位の小冊で、読みやすいので一気に読めるし、読み返すとまた味わいが出る。学生さん達にも読んでいただき、「人間の生き様」を考えていただくのに格好のチャンスと思う。おそらく気に入って、新しい観点から関連する著書や小説も読みたくなるのは請け合いである。
1)太宰治と聖書 (野原一夫、 新潮社)平成10年5月発刊[※910.26/N 93開架]
芥川龍之介と太宰治は、ある意味ではキリスト教信者からすれば評判は良くないが、わが国の小説家の中では、最も真剣に聖書を読み、その一語一句を噛みしめて理解しようと努力した人ではないかと思う。
本書は、太宰がなぜに聖書に感銘を受け、悩まされて小説を書いてきたかを年代別に、かつ聖書の章句と比較しながら、解説を加えている。著者の野原一夫氏は、旧制浦和高校文芸クラブ時代に太宰に面接している。本格的に面識を得たのは第2次大戦が終わり、昭和21年11月に、太宰が疎開先の津軽から東京三鷹に帰り、流行作家として活発な文筆活動を始めた時より、昭和23年6月に玉川上水への入水心中自殺までの約一年半あまりの生涯を終える期間である。新潮社を皮切りに、出版や編集の仕事の面のみならず、大学の後輩としても、特に太宰にかわいがられて、私的にも親密な交流があった。野原氏自身も太宰の作品を通して才能の素晴らしさや、実直な人柄に心から尊敬の念を抱いていたものと思われる。
「回想 太宰治 新潮社 野原一夫 昭和55年」[※図書館書庫(910.28/N93)]
周知のごとく、太宰治(本名 津島修治)の生涯は、惨々たるもので、自他共に認める人間失格者そのものであった。
昭和5年、津島家の大いなる期待を担って、東京帝国大学文学部に入学したが、殆ど登校せず、弘前高校時代より馴染みとなった芸者、初代と同棲、またマルキシストとして、非合法運動に加わり、特高警察に追われるなど、終に直接の影響が郷里に及び、実家の津島家から除籍、勘当を受けた。その後、非合法運動からは離脱できたが、大学は卒業できず、家族やマルキシストの友人を裏切った自責の念も強く抱いたまま、昭和8年、25才のとき太宰治を筆名として、自ら志した作家生活を始めることになる。同人雑誌への太宰の作品は、識者への共感を呼んだが、「人間失格」の意識が強く、鎌倉での心中未遂事件、昭和10年、急性盲腸炎に併発した腹膜炎の鎮痛、鎮静のためにバビナールが注射され、退院後も中毒症状が絶えず、家族や社会から狂人の扱いを受けるに至った。妻の初代が家族や、井伏鱒二と相談して、精神病院に入院、太宰は施錠された、「人間倉庫」に移された。禁断症状がとれ、精神科医師の状況判断で、太宰が希望したうち、聖書だけが読むことを許された。太宰は聖書を読み、時に救われたが、さらに聖書の内容を追求して、自分の作品を書こうと決心したのはその時であったと
著者は述べている。その後の太宰の作品の多くが、聖書を意識してのものが多いが、野原氏は太宰研究者の多いなかで、彼の作品を聖書との関連で捉えている者は少ないという。聖書研究家である、赤司道雄氏は自著、「太宰治-その心の遍歴と聖書 八木書店 昭和60年」[※購入手続き中]の中で、特に太宰の作品は聖書研究の対象として、また日本精神史を理解するうえでも意義が深いこと、また太宰が聖書を最も良く読み、その理解者であったことを認めている。野原一夫氏にも、この点では同意しているものと思う。精神病院より退院後、太宰はイエス・キリスト伝を書こうと決心したが、イエスがあまり偉大で、畏敬の念がとれず、かえって反発してイエスを裏切ったユダに共感を得て、太宰流の解釈で3年後に「駆け込み訴へ」を完成させている。「己を愛するごとく、汝の隣人を愛せよ」これが最初のモットーであり、最後のモットーです、と太宰は書いている。
2)フランクル回想録-20世紀を生きて (V.E.フランクル、訳 山田邦男、春秋社)
1998年5月発行[※購入手続き中]
本著は20世紀の偉大な精神科医ヴィクトル・ E.フランクルが自ら自伝として著したもので、独乙語の直訳では(我が書物に記されざりしこと
- 回想録)となっている。訳者の山田邦男氏は人間形成論、哲学的人間学専攻の方で著者のフランクルも晩年に会われて直接話をされた様である。フランクルは20世紀の精神科医としてフロイド、アドラーに並んで3本指に数えられるが、ナチスによるアウスシュビィツ収容所の体験記「夜と霧」[※945.9/F
44開架]さらに悩める人々に希望を与える講演集「それでも人生にイエスと言う」[※114/F
44開架]は有名で、世界各国に訳文が出ている。後者は本書の訳者山田氏が担当されている。フランクルはユダヤ人として生れ、ナチスためにアウスシュビィツに送られ家族や妻も殺害されている。フランクルは既に
4才で「人生の無常さが人生の意味を無に帰してしまうのではないか」と云うことを考えたとのことである。医学部学生時代から精神科医になろうと決心し、ウィーンでの若き精神科医時代にはひそかにナチスムに抵抗した。明らさまな抵抗運動ではなく、自分自身が何としても生き延び自分の人生や存在を無為にしないという志が原点にあった。この点太宰の生き方と根本的に異なるものである。アウスシュビィツでは死が明日かと云う時においても、フランクルが目指していた「医師による魂の癒し」の本を書き残そうと努力した。第二次大戦が終わり、開放され、フランクルはアウスシュビィツの体験に基いて「人間が生きることへの意志」の重要性を強張した。また共同責任に反対する立場からナチ親衛隊員をも擁護する立場を自から毅然としてとり、アメリカやユダヤ人社会からも複雑な目で見られた。 民族や社会環境や社会通念(時にニヒリズム)あらゆる苦悩にとらわれることなく、「人生の問い」に答えられるためには、自らの存在そのものについて責任を担わなければならない。特にそれは人生への肯定である。
また、訳者の山田邦男氏は、フランクルの思想に関する解説を本書に加えており、読者には参考になる。「精神が完全に根源的であり、完全に自分自身であるその場所において、精神は自分自身に関して無意識である。」
教育学部 藤田 達生
津藩は、伊勢国津に藩庁を置き、伊賀一国と中部伊勢などの32万石余を領有する大藩であり、藩祖は名築城家として知られる藤堂高虎であった。日本史担当教官として当地に赴任した直後、私にとってまことに残念に思われたのが、公園化によって破壊の進んでいる津城跡に象徴されるように、かつての城下町のよすがとなる建造物・町並みなどが意外に少ないということである。
江戸時代、津は伊賀街道と伊勢街道が交わる流通の結節点に位置する宿場町でもあり、伊勢音頭に謡われるほど殷賑をきわめ、東海地域を代表する都市のひとつに数えられた。しかし近代以降の都市計画は、かつての城下町の伝統と共生するのではなく、否定する方向で進められたようである。
このように歴史的な景観が失われつつある近年ではあるが、喜ばしいこととして指摘したいのが、地元研究者のたゆみない努力によって、津藩の編纂物が逐次翻刻・刊行されていることである。
津藩はその初期から、文化的な事業に積極的であった。ここでは高虎に関わる藩正史である、『高山公実録』(上野市古文献刊行会によって1998年に清文堂出版株式会社から刊行)・『宗国史』(上野市古文献刊行会によって1979・80年に同朋社出版から刊行)・『太祖創業志』(のちに増改され藩主高兌撰として『聿脩録』と改題・版行され、1930年に『補注国訳聿脩録』として高山公三百年祭会から刊行)について、簡単に紹介したい。
まず『高山公実録』は、藩側が作成した藤堂高虎の一代記であり、きわめて精度の高い分析が試みられているが、惜しいことに編纂者・成立年代ともに不明である。『宗国史』は宝暦元年(1751)に藤堂高文によって、『太祖創業志』は文政元年(1818)に藩校有造館の督学であった津阪孝綽(もとひろ)によって著されたものである。なおこれらの刊本は、いずれも本学附属図書館で架蔵している。
なかでも特に著名なのが、『宗国史』である。これは、全102巻からなる。編纂者は藤堂高文、校訂者は甥の高芬(たかか)である。内編には初代藩主高虎から、二代高次・三代高久までの事績を、外編には一族の功績・藩法・村人口・戸数・寺社などについて詳細に記されている。
藤堂高文(1720~1784年)は、江戸時代中期の津藩漢学者であって、藤堂出雲家六代で幼名三郎助、字は子樸のち大樸、号は東山を称した。藤堂高武の第6子として誕生したが、兄高豊が久居藩主となったため家を継ぎ、7000石の騎将となったが、故あって宝暦元年には隠居し、乙部の別荘で生涯を過ごした。この致仕の年に完成したのが、『宗国史』である。彼は、このほか『元和先鋒禄』など多くの著述を残している。
なお『宗国史』の写本については、藤堂宗家と旧藩校有造館(津)・崇広堂(上野)などで保存されていたが、前二者は失われており、崇広堂に残った写本32冊を底本として公刊された。
このように藤堂高虎や初期津藩の研究も、近年ようやく本格化する条件が整ったといえよう。そこで来年度からは、これらの藩正史を相互に比較・検討する研究会をもちたいと考えている。興味のある方は、ぜひご参加いただきたい。
 このほど附属図書館に『百部叢書集成』が入った。この書は1968年に台湾で刊行され、百種の叢書が集められている。すなわち『百部叢書集成』という書名は、そのものずばりで全く何のけれんもない命名なのである。しかし線装本(和綴じ・糸綴じ)7950冊、830帙という分量は、それだけで人を圧倒するものがある。
このほど附属図書館に『百部叢書集成』が入った。この書は1968年に台湾で刊行され、百種の叢書が集められている。すなわち『百部叢書集成』という書名は、そのものずばりで全く何のけれんもない命名なのである。しかし線装本(和綴じ・糸綴じ)7950冊、830帙という分量は、それだけで人を圧倒するものがある。
集められた百種の「叢書」とはそもそもどのような書物なのか。それは、種々の著作を集めてひとくくりにまとめたものと言うのが簡単な定義であろう。ゆえに、○○叢書というある叢書には複数の著作が入っていることになる。『百部叢書集成』はそのような個々の叢書をさらに集めた叢書の名ともいえる。叢書という言葉自体は、韓愈や陸亀蒙といった唐代中期の文学者に既に用例があるものの、ここで定義した意味での叢書は、宋の嘉泰二年(1202)に刊行された『儒学警悟』、咸淳九年(1273)刊行の『百川学海』に始まる。
書くという行為を重視し、書かれたものを大切にする中国では、著作は膨大な量にのぼる。そこで能率的に知識を整理するため、或いはたとえば学問観や文学観といったある統一された方針をもって著作や作品を選択・選別するという、編纂や編集といった作業が古くから行われてきた。今風に言うとエディションの伝統があり、叢書もそのバリエーションと見なすことができるのである。そのため叢書の編纂は、「叢書の学」とでも呼ぶべき一種の学術的行為としてその価値が確立している。中国学において叢書は内容別に次のように分類される。(1)家叢。ある一人の著作をまとめたもの。(2)専叢。中国の伝統的な図書分類法、経(儒学関係)、子(儒家以外の諸子)、史(歴史)、集(文学)など、いわゆるあるジャンルについての著作をまとめたもの。(3)古逸。古い時代のあまり一般に見ることのできない著作や、佚文(失われた著作・作品)を再編集したもの。(4)雑叢。個人がもつ蔵書、珍しい著作、版などをまとめたものなど。
より簡単に言えば、叢書は専門的学問の便のためと、極めて珍しいテキストの公開といった目的で編纂されたといってよかろう。ゆえに叢書は、書誌学において重要な意味をもつばかりでなく、すべての学術の基礎として、さらにある時代、またはある時代までの各分野の学術の水準を端的に知るうえで極めて高い資料的価値をもっているのである。
『百部叢書集成』もこのような伝統のうえにある。この書は叢書を単に機械的に百種集めたわけではない。それら叢書に収められている著作は合計すると6000、そのうち重複する約2000について7年の歳月をかけ、ひとつひとつ校勘、補訂、考証等を行い、最終的に最良の版本として4874の著作を選定収録しているのである。すなわち『百部叢書集成』とは、上の4つの類の叢書を網羅し、叢書の歴史の最初に位置するものから中国の古典的世界の一応の終了である清末期までの約800年間の、人間の知的探求心と熱意によって編纂されて続けた成果を集大成したものなのである。
百種の叢書すべてを解説する余裕はないので、興味深い叢書三種について簡単に述べ、以てこの書の紹介に代えたい。
ひとつは清の光緒年間に陸心源によって刊行された『十万巻楼叢書』である。編者の陸心源は帰安(浙江省)の人。清末四大蔵書家の一人で、中国において木版印刷が始まった宋代に印刷されたテキスト(宋版)を二百種集めたことに因んで書室を百百宋楼と名付けるなど、書籍を愛し貴重な蔵書多数を所有していた。その彼が蔵書のなかから宋版を中心に珍しい版本を選んで出版したのが『十万巻楼叢書』である。ちなみに日本の図書館で宋版を所蔵している所は、すべてそれらを貴重書として大切に保管している。しかし陸氏ほどの量を所蔵しているところは稀である。その稀な所のひとつに岩崎財閥ゆかりの静嘉堂文庫があるが、実は陸氏の蔵書を購入したものである。このように財力によって貴重な書籍を一気に持ってきたこともあるが、日本人が古来中国書を「舶来品」として大切に保存してきたことはよく知られている。『百部叢書集成』のなかには日本のそのような学術を尊重する伝統が貢献した叢書が二種入っている。光緒年間に黎庶昌によって刊行された『古逸叢書』と日本の林述斎が編纂した『佚存叢書』である。前者は黎氏が全権公使として日本に駐在していたときに、その属官で書誌
学者として有名な楊守敬とともに、中国では失われてしまって日本にのみ伝存する佚書や優れた版を翻刻したものである。後者も同様の趣旨で編纂された叢書である。林述斎はその姓からわかるように幕府の学問に責任をもつ林家の人間で、大学頭の職にあった。彼も寛政11年(1799)から10年がかりで日本にのみ残されていたテキストをあつめてこの叢書を編纂したのである。
叢書の編纂において、編纂の目的と方針をたて、それにふさわしいテキストを選択収集するというエディターの役割は極めて重要であり、その叢書の価値は編者の見識にかかっていると言っても言い過ぎではない。さらに上記の三叢書の編纂の経緯からもわかるように、叢書の刊行は編纂者の自分の知見を公開しようという公的精神と、より優れた学術を得たいという読者の熱意とによって支えられている。すなわち、ある共通の知的世界が存在しなければ、叢書という書物は成り立たないのである。そして日本人が編纂したものや日本に残るテキストが納められている『百部叢書集成』は、その世界が広く東アジア全域を覆っていたことを示している。
このように叢書はそれ自体がひとつの専門性をもった、いわば図書館のような役割ももっている。とするとそれらを集大成した『百部叢書集成』は一大図書館と言ってもよかろう。図書館が建築物としてのみ評価されたとしたら、それは図書館が本来期待されている機能を十全に果たしているとはいえない。それと同様に、『百部叢書集成』もその大部であることによって人を圧倒するだけで、いたずらに「高閣に束ね」られていることは本意ではあるまい。ぜひ一度手にとり、少なくともある時期までは東アジア地域において共有されていた教養の世界を実感していただきたい。
《図書館での整理が終わりました》
目録は各叢書単位で作成されており、内容細目までは入力されておりません。
[例] 「咫進斎叢書」は「咫進斎叢書」「シシンサイ」「シシンサイ ソウショ」から検索できます。ですが、この叢書に含まれる個々のタイトル、たとえば「大雪山房雑記」からは検索できません。別冊の索引が2部備付けてありますのでそれをご覧ください。
(ご寄贈順)
□パソコンコーナーと語学学習室の整備
すでにお気づきの方も多いと思いますが、貸出カウンター前のパソコンコーナーを用途別に配置替えしました。ウィンドウズの最新マシーンも自習用として何台か確保してあります。今回は留学生センターの協力もあり、このコーナーのみならず、2階の語学学習室にもパソコン、ソフトを備付けることができました。このようなコーナーはいろいろなレベルの利用者が使用します。利用に際しては以下のことがらに注意を払っていただき、これからもこのようなサービスを図書館が提供できるようご協力ください。
いろいろ「試してみる」ことはかまいませんが、後を「きれいにしておく」ようにしてください。自分に使いやすいよう、スタートメニューのショートカットアイコンを変え、いくつかのディレクトリーを作成し、ダウンロードしてきたソフト等を格納していた人がいました。隠しファイルを下位のディレクトリーに「隠して」いる人もいます。
電源が不足していますが、3月末までには工事できる予定です。また、各パソコンで何ができるかなどの案内の詳細は別途行います。また参考調査係でのガイダンスも随時受付けていますのでご利用ください。