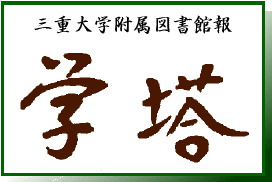
No.103 1999. 9. 20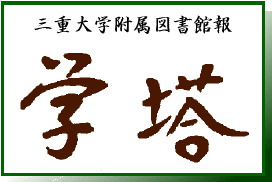 |
目次 |
![]()
 三重高等農林学校図書館〜農学部分館 (大正13年〜昭和40年) |
 (竣工から昭和初年頃の高農図書館閲覧室) |
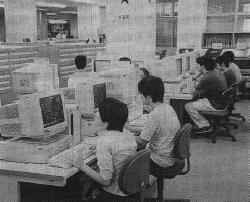 |
 現在の附属図書館(昭和53年〜) |
![]()
約束の時間の数分前、ドアをノックしようか否かためらっていると、内側からドアが開いた。「いらっしゃい」という声と笑顔、緊張が一気に解けた。
3年前のある日、米国でのことである。その1年前から、ふとしたきっかけで私の専門分野における権威(以下「先生」)の一人と共同研究を始めていた。以後、電子メールでのやり取りをしていたが、私が学会報告のため渡米することを告げると、「ちょうどいい。もし時間が許せば訪ねていらっしゃい」ということになった、その時の情景である。
招かれて研究室に入ると、思いのほかこぢんまりとした部屋で、人文学部の標準的研究室よりやや狭いぐらいだった。机・テーブル・キャビネット・パソコン・書棚が機能的に配置され、よく整頓されているのに驚いた。先生は、「なに、君が来られるので慌てて整理したんだよ」とにっこり笑われた。挨拶もそこそこに1時間ばかり研究の話をした。
研究上の疑問点について糺(ただ)し、今後のスケジュールについて確認を済ませたちょうどその時、ノックの音が聞こえた。「どうぞ」「失礼します」――入ってきた学生が、分厚い封筒を抱えている。私に会釈をして、先生に「ご依頼の資料です。リストの最後の本は明後日には届くそうです」と告げ、封筒を渡した。
「紹介しよう。彼は私のRA(研究助手)の一人で、名前はマイク。修士論文を提出したばかりで、今は夏休みだが、『ランナー』をやってもらっている」と先生。「ランナー、ですか?」「この大学ではそう呼んでいるんだ。ほら、研究に必要な論文や本を図書館から借りてきたり、コピーを取ってきてくれる助手だよ。あれ?君のところにはいないのか?」。
残念ながら、公式サービスとしての「ランナー」(通常「ライブラリー・ボーイ」)は日本の大学では皆無であろう。RAとしてランナーをする代わりに、学費を大幅(半額)に免除されているという。教官の研究をサポートするため、頻繁に図書館とコンタクトを取り、最終的には必要と思われる資料に自発的に目星をつけ、探し出して調えるのが優秀なランナーの条件なのだという。
マイクがついでに買ってきてくれたサンドウィッチを食べながら、我々は、研究に対する図書館の役割について話した。「大学院生の立場で言うと」マイクが言った。「やはり院生個人の机が書庫にあるのはありがたいです。本を何冊も使って調べ物をしているときは、毎日本を元に戻さなくても、積んでおけますから・・・後は、どんな本でも所蔵がなければ3日ぐらいで取り寄せてくれます」。先生曰く、「研究室が狭いだろう? だから本当によく使う本しか置けない。でも図書館が充実しているから、ほとんど困ったことはないよ。遅く(深夜12時)まで開いているしね。でも、それ以上にサービスが充実しているのが大事だと思うね」。「私もそう思います」とマイク。「ランナーは、図書館サービスの担い手ですね。この仕事をしていると、資料収集の勉強にもなりますし、研究者の仕事がどういうものか分かってきます。研究を側面からサポートしてくれるサービスが貧弱だったら、図書館はただの『本置き場』になってしまうでしょう」。マイクのしっかりした意見に、先生はにこにこと微笑んでいた。
翻って、三重大学附属図書館はどうであろうか。私の目には、ここ数年のサービス向上(特に電子化・ネットワーク対応)とビジョンの明確化は顕著なものに見える。今後も可能な限りのサービス向上がなされることを切に願っている。
医学部看護学科 中西貴美子
コソボ紛争、飛行機ハイジャック事件、大雨や地震による被害など、人の生死にかかわる出来事は、いつも最大の関心事として新聞の1面を飾る。これらの出来事は、いわゆる三人称の死であって、関係者以外の人であれば、自分からは遠く離れたところで起こっていることにすぎないと感じるのも無理のないことだろう。それでも先頃行われた脳死体からの臓器移植は、自分や自分の家族など身近な人に関わる問題として認識している人が多いようで、意思表示カード(ドナーカード)を所持する人が多くなっていると聞く。
人は病気であれ、事故であれ、天災であれ、いずれ必ず死を迎える。そして、その迎え方は医療の格段の進歩によって選択の幅が広がり、自分で自分の生き方・死に方を決めなければならない時代になってきている。折しもオランダでは安楽死が法制化されようとしている。そのときのために準備しておく、とまではいかなくても、若いうちに一度死について考えてみるのも、無駄ではないだろう。そこで、ぜひ「死」に関する書物を読むことを奨めたい。
読むと言っても、書店の店頭には「死」に関する書物が氾濫している。闘病記や脳死に関するもの、果ては死体の写真集までそろっている。数年前、若い女性向けの月刊誌の表紙に「特集死」と書かれているのをみて驚いたことがある。タブーでなくなるのは、いいことだと思うが、死を語ることがファッションになってしまうのは考えものだ。もちろん死についてのアプローチの方法は様々あるが、上述の趣旨から言えば、三人称の死を扱ったものではなく、二人称あるいは一人称の死について書かれたものがよい。
ブックガイドとして「死への準備教育のための120冊」A.デーケン(吾妻書房)、「素晴らしい死を迎えるために−死のブックガイド」加賀乙彦(太田出版)が出ているので、これらを参考にしていただくのがよいが、ここでは私個人の非常に限られた読書歴の中から、読みやすいものをいくつか紹介したい。
・E.キューブラー・ロス「死ぬ瞬間」読売新聞社:本学図書館にも複数冊あるエポックメーキング的な書ではあるが、意外に学生には知られていないため、あえて取り上げた。死に直面した患者の生の声がそのまま収録されている。著者の自伝である「人生は廻る輪のように」(角川書店)とあわせて読むことをお奨めする。
・岸本英夫「死を見つめる心」講談社文庫:宗教学者という三人称の死を見つめる立場から、死期が近いことを知り死を一人称として考えなければならなくなった著者の思いが語られている。
・柳田邦男「犠牲−我が息子・脳死の11日」文藝春秋:死の問題を扱ってきたライターである著者が、自殺を試み脳死となった息子の父親という立場に立たされた時の苦悩を描く。
以上、読書の秋・考える秋にひとつ繙いてみてはどうだろうか。
図書館から
文中で紹介された図書の三重大学での所蔵状況は下記のとおりです。
「死ぬ瞬間」 配置場所:図書館・開架,医短・図書室(請求記号:146/Ku11) 「死ぬ瞬間・続」 配置場所:図書館・開架,医短・図書室(請求記号:146/Ku11) 「新・死ぬ瞬間」 配置場所:図書館・開架,医短・図書室(請求記号:146/Ku11) 「死ぬ瞬間」(完全新訳改訂版) 配置場所:図書館・開架,(請求記号:146/Ku11) 「死ぬ瞬間・続」(完全新訳改訂版) 配置場所:図書館・開架,(請求記号:146/Ku11) 「人生は廻る輪のように」 *購入手続き中 「死を見つめる心」 配置場所:図書館・開架,医短・図書室(請求記号:915.9/ Ki58) 「犠牲(サクリファイス):わが息子・脳死の11日」 配置場所:図書館・開架,医短・図書室(請求記号:915.9/Y53)
三重県が準備を進めてきた「三重県図書館情報ネットワーク」が、平成11年3月から、「MILAI」(Mie
Library Advanced Information Network System)という愛称とともに正式にサービスを開始しました。
MILAIの特徴は、「全ての図書館を全ての利用者に」という理念のもとに、館種を越えた様々な図書館が参加して県内図書館の総合目録データベースを構築し、オンラインによる図書館間の相互貸借を行っていることです。現在、県立、市町村立の図書館、公民館図書室、大学、短大、高専の図書館、県立学校など、48館(蔵書データを提供する図書館は31館)が加盟しています。登録済データ数は既に200万件に達し、今後、ネットワーク加盟館やデータ提供館の増加に伴い、総合目録としての機能を一層充実していくことが期待されます。
本学図書館についても、今年7月に他の大学図書館に先駆けて蔵書データ(初回登録分として、附属図書館に配置してある資料のうち約5万件)の登録を行い、ネットワークの一員として相互貸借業務を開始しました。昨年12月には、学外者への館外貸出を始めたところですが、MILAIへの参加は、直接大学を訪れることができない利用者がインターネットを介して本学の蔵書データを検索し、普段利用している公共図書館などを通じて資料を手にすることができるという意味で、地域社会に開かれた図書館としての取り組みをさらに一歩進めることでもあります。
また、大学の構成員にとっては、附属図書館や研究室のパソコンから、県内の多くの図書館の蔵書目録をひとまとめに検索することができるようになったわけです。探している資料が見つかったら、附属図書館の参考調査係を通じてオンラインで借受依頼を行うことができ、これまで以上に資料の入手が容易になると考えられます。
MILAIのホームページのURLは、http://ufinity02.jp.fujitsu.com/milai/
です。附属図書館ホームページのリンク集からもアクセスできますので、是非ご利用ください。
(平成11年4月〜8月)
| 内容 | 日程 | 回数 | 参加者数 |
|---|---|---|---|
| 図書館オリエンテーション ・対象:主に新入生 |
4月12日〜23日(月〜金) | 26 | 187名 |
| CA利用オリエンテーション ・対象:大学院、生物資源研究科生 (指導教官、丹羽教授) |
4月19日 | 1 | 12名 |
| オリエンテーションゼミナール ・対象:人文学部オリゼミ受講者(米川教授) |
4月26日、7月5日 | 2 | 38 |
| 中国語によるオリエンテーション ・対象:留学生 ・案内役:祖国威氏(大学院生)*別掲「総括報告」 |
6月21日〜25日(月、水、金) | 3 | 50 |
| 図書館ツアー | 7月5日〜16日(月、水、金) | 6 | 18 |
| 社会教育主事講習・図書館オリエンテーション | 7月15日 | 1 | 103 |
| 学校図書館司書教諭講習・図書館オリエンテーション | 8月2日 | 1 | 57 |
| 閉架書庫利用指導 | 4月〜8月 | 6 | 26 |
留学生たちにできるだけ早く図書館の利用方法を理解して、存分に図書館―この重要な情報源―を活用してほしいとの願いで、三重大学附属図書館と中国留学生学友会は6月中旬に中国語オリエンテーションを共同主催した。
今回の活動が主に中国語を使い慣れている留学生に対して、全て中国語を使って解説した。
今回のオリエンテーションは留学生の中で反響は大きく、3分の1近くの中国の留学生が参加しており、最近における大きい留学生の活動となった。
多くの留学生は収穫が大きいと思っており、今後、図書館がもっと多くこのような類似する活動を催すのを望んでいる。
近年、日本の国際交流の展開に従って、来日の中国の留学生は絶えず増加している。
三重大学の中国の留学生は150人に達して、留学生の総計の4分の3を占める。
これらの留学生の中で多くの人は言語の障害のため、また図書館の利用知識が不足していることから、十分に図書館を利用することができなくて、日常の勉強と研究の中で資料を探すためにあれこれの困難に出会っている。そのためにこのようなオリエンテーションを催すのがとても重要であり、今後とも繰り返し開かれるべきだと思う。
総じて言えば、準備がよく整っていたことと、留学生の態度が積極的だったので、今度のオリエンテーションは非常に成功であった。
オリエンテーションを通して、留学生は図書館に対して理解が深まり、多くのものを学んだようである。
しかし、時間が短かかったため、表面だけざっと見て図書館サービスに対して簡単な紹介をすることしかできなかったことは反省すべきだろう。
たくさんの留学生はまだ多くの疑問を持っていて、満足と感じていない。 今後のオリエンテーションをもっと良いものとしてゆくために、私は以下のいくつかの裏側の仕事を強化すべきだと思う。
1.宣伝
今度のオリエンテーションにこんなに多くの留学生が参加したのは、宣伝に力を入れたからである。
このために図書館と学友会は多くの仕事をした。 しかしそれでも一部分の留学生は知らせを見ていないためにオリエンテーションに参加していない。非常に残念に思う。
今後のオリエンテーションではいっそう宣伝を拡大するべきで、学内刊行物で、特に図書館報とinternet上の附属図書館のhomepage中で知らせを出すことが必要だろう。それとともに、学生が図書館がただ図書を借覧する場所と考えているような誤りに対して、図書館オリエンテーションの重要性を宣伝の中で強調するべきだろう。
2.オリエンテーションの内容
今度のオリエンテーションの中で紹介した各サービスのうち、留学生が比較的興味を持ったのはふだんあまり熟知しなかったプロジェクトで、例えば集密書庫、語学学習室、参考図書、情報検索コーナー、OPAC等である。
そのためこれからのオリエンテーションではこれらを重点的に紹介すべきであり、たとえば図書の貸出、返却、閲覧等の基本的なサービスについては簡単な紹介だけでもう十分である。
またこれから常用されるはずの検索データベース、電子図書(CD-ROM)、参考図書の使用方法、また留学生が最も関心をもった中国語internetと中国語の文書エディターソフトを紹介すべきだと思う。
3.オリエンテーションの形式
今度のオリエンテーションは主に解説の形式をとったので、留学生は一部の内容に対して恐らく完全に理解することはできなかっただろう。
もし解説とあわせて、すべての参加した学生が実際に体験できれば、例えば情報検索の機器や自動貸出システムなど、もっと良い効果をあげただろう。
4.アンケート
図書館利用者からのフィード・バック情報の収集は図書館における重要な日常仕事である。
今回オリエンテーションの最後に、すべての参加者は1枚の簡単なアンケートを書いた。
このアンケートを通して今後の留学生に対するサービスを展開することに役に立つデータを収集することができる。
そのため、アンケートの内容は更にいくつか充実させるべきだ。 例えば留学生が図書館を使っていてよく出会う困難、サービスの現状の評価、満足しなかったサービスと満足しているサービス、図書館員に対する評価などの質問を加えるべきだ。
アンケートの形式は選択肢がある回答のやり方を採用するべきで、回答者にできるだけ少なく時間を使わせて、少なく字を書いて、たくさん質問に答えてまた反感を引き起こさないようにする。
要するに、今回のオリエンテーションは図書館が留学生のためにしたひとつのよい事であり、私は三重大学の中国の留学生を代表して附属図書館に向って心から感謝する。
(*印は学外のサーバにアクセス)
○学内ネットワークから利用できるもの
| 名 称 | 内 容 | 収録範囲 | 備 考 |
| *雑誌記事索引ファイル | 学術誌・大学紀要・専門誌の論文・記事情報 | 1984年〜現在 | 図書館に専用端末有 |
| *ジャーナルインデックス | 総合誌、一般誌を中心とした身近な記事情報 | 1981年〜現在 | 図書館に専用端末有 |
| *FirstSearch | OCLCが提供するオンラインレファレンスサービス 主なデータベース:ArticleFirst, ProceedingsFirst, ERIC, PAIS, etc. |
図書館に専用端末有 | |
| CA on CD | Chemical Abstracts のCD-ROM版。 | 1996年〜現在 | Mac & Windowsで利用 |
| 平凡社世界大百科事典 | Windowsで利用 | ||
| OED | 2nd ed. | Windowsで利用 | |
| 広辞苑 | 第4版 | Windowsで利用 | |
| 現代用語の基礎知識 | 1998年版 | Windowsで利用 | |
| 民力 | 1989〜1997 | Windowsで利用 | |
| 朝日新聞見出しデータベース | 1945〜1989 | Windowsで利用 | |
| Dictionary of Organic Compounds on CD-ROM | 有機化合物事典 | Windowsで利用 | |
| Library of the Future | 1st ed.& 2nd ed | Windowsで利用 | |
○図書館の専用端末から利用できるもの
| 名 称 | 内 容 | 収録範囲 | 備 考 |
| *BOOKPLUS | 国内最大の書籍情報 | 昭和初年〜現在 | |
| Current Contents | Agri,Bio,Environ Science: Life Science: Phys,Chem,Earth Science | 1998〜 | |
| CD-HIASK | 朝日新聞の全文記事 | 1985〜1998 | 貸出カウンターで受付 |
| CD人情報 | ビジネス・経済・政治 | 貸出カウンターで受付 | |
| BUNSOKU(科学技術文献速報) | 化学・化学工業編(国内編) | 1995〜1998 | 貸出カウンターで受付 |
| BUNSOKU(科学技術文献速報) | 機械工学編、環境公害編、土木・建築工学編 | 1997〜1998 | 貸出カウンターで受付 |
| 理科年表CD-ROM99 | 大正14年の初版から平成11年版までの理科年表72冊分 | 貸出カウンターで受付 |
※「本学教官著作コーナー」展示ケースに配架しています。貸出可能です。
![]()