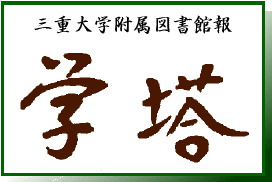
No.104 2000. 2. 21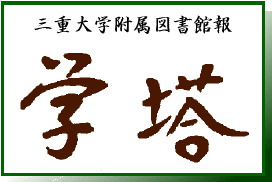 |
目次 |
![]()
![]()
1999年11月30日で、三重大学附属図書館が、公共図書館なみのごく簡単な手続きによる、一般市民への貸出しを開始してから、まる1年となりました。
貸出条件もほぼ学部学生と同等ということで、当初数多くのマスコミに取り上げられ、利用券(貸出証)の交付数は順調に伸びていきました。
1998年12月から1999年3月までの年度内4ヶ月間で、171枚(月平均42.8枚)。その後も順調に推移し、1年間では、640枚(12ヶ月間の月平均53.3枚)に達しています。入館者数は延べ3,901名です。
4月の年度替りで、引き続いての利用を希望する人は再度の交付が必要ですが、約20%の人がその手続きをしています。
貸出しは1,395冊あり、社会科学、自然科学が多数を占め、文学は少なく、公共図書館とは異なる分布を示しています。登録者のうち、他大学の学生・教官の占める割合は低く、多くは一般市民です。大学構成員の需要が以上のような分布をつくり出したのではないことがうかがわれます。もっとも、これだけでは公共図書館に対するものとは異なる大学図書館特有の図書館需要があるのか即断しかねますが、津市民の占める割合が21%であり、登録者の分布が全県的に広がっていて、かなり遠方からの利用者が数多くあることは、市民の大学図書館への期待が大きいものであることを示しています。
身分別登録者数
| 大学関係 (22%) |
一般市民 (78%) |
分野別貸出
| 社会科学 (28%) |
自然科学 (22%) |
文学 (14%) |
その他 (36%) |
工学部 浦山益郎
日本社会は成長期から成熟期を迎えようとしています。成熟社会になると、人々は経済的な豊かさばかりでなく、住むことの意味に重きをおくようになるといわれています。便利ならばどんな都市でもよいというわけではなく、住むに値する都市が求められるようです。都市の個性、豊かさが感じられるまちづくりとは、そのような文脈で語られるキーワードです。人文学部 西村智朗
高度情報化社会へと進みつつある今日、大学の研究・教育の在り方はどのように変わっていくのだろうか?かなり散漫ではあるが、考えていることを綴ってみたい。
まず、情報収集のための環境は、目覚ましく進歩したといえる。私は研究の必要上、国際機関の公式文書を入手しなければならないことが多い。つい数年前までは国連寄託図書館である愛知県図書館に、そこにない場合には東京の国連広報センターまで出向かなければならなかった。これは地方の研究者にとっては大きな障害である。ところが今日、国連のみならず、他の国際機関や国際会議の文書は一両日中にはインターネット上で公開され、容易に入手することができる。おそらく他の学問領域においても同様のことが言えるであろう。その点で、インターネットの普及は、情報の東京一極集中という壁をかなりの程度崩壊させたと思われる(残念ながら既存文書はデジタル化されていないので完全崩壊とまではいかない)。
そしてインターネットに代表される高度情報化の流れは情報の高速化と大量化を導いた。経済学者の野口悠紀雄教授(東京大)によれば、日本人の紙の使用量は、現在5人家族で1年間に1.5トンであり、50年前の24倍になっているそうである(『「超」整理法3 とりあえず捨てる技術』中公新書・1999年、より)。そのことが重大な環境問題を引き起こしていることも憂慮すべきだが、ここではそのことによる我々の思考様式の変化について考えてみたい。
高速かつ大量の情報が我々の前を通過していく中で、我々は必要な情報と不必要な情報を瞬時に判断しなければならない(それらは読み終わるまで「必要か不必要か」は判断できないことが多いのでかなりタチが悪い)。おそらくそのこと事態は避けられない現象であり、好むと好まざるとにかかわらず我々は的確な判断力を身につけていく必要がある。しかし、そのことにより我々は一つの物事をじっくり考える習慣を忘れ、正確に他者に伝えるという作業を疎かにしてはいないだろうか?
このことは大学の研究・教育と密接に関わってくる問題である。教育改革・大学改革の中で、大学はより「効率的」で「現実的」な研究成果や教育成果の達成を求められている。社会のニーズを無視してはならないのは当然のことだが、期限や結果に縛られない、自由な発想でじっくりと地に足をつけた研究や教育は今後大学では必要ないということであれば、上記の要求は大学の存在意義にかかわる重大な挑戦である。
再度インターネットに一例を求めれば、そこにはBBS(Bulletin Board System:電子掲示板システム)など、いつでも自由に発言できる空間が存在する。興味本位に少し覗いてみると、天下国家のあり方から、ドラマの結末予想まで、そこにはありとあらゆる意見や情報が展開されている。その利用者の多くは大学生を含む若い世代であろう。しかしよくよく眺めていると、誤字・脱字、他人に対する誹謗中傷、そして著しく一方的・一面的な発想が散在している。情報の高速化がもたらす恐怖感(「早く発信しないと誰も見てくれない」)であろうか、それとも匿名性がもたらす安心感(「誰が書いたかバレない」)であろうか、「旅の恥は“掻き捨て”」ならぬ「ネットの恥は“書き捨て”」が横行していることが少なくない。愚考するに、物事を深く考える洞察力、言葉を慎重に使おうとする配慮は、高度情報化社会においても必要な、いや高度情報化社会であればなおのこと見直すべき才能ではないだろうか。情報化がもたらす社会現象とそれに対応する大学教育の在り方について、大学関係者の中でもっと議論があってしかるべきである。
蛇足かもしれないが、大学運営に効率性が求められ、競争原理が導入されようとする昨今、少なくとも大学図書館においては、高度情報化社会への対応を進めていく一方で、従来の大学らしい研究・教育空間(具体的には基礎研究を重視した文献の収集と管理)の維持・発展をこれからも切望したい。
附属図書館では、昨年12月1日に図書館業務システムの機種更新を行いました。今回の更新にあたっては、データ量の増加や業務の電算化の促進に対応するために機器の性能の向上を図ることと、利用者用サーバを活用して電子図書館的な機能を強化し、利用者サービスを充実することに重点を置きました。
利用者用サーバでは、従来のOPAC(オンライン蔵書目録検索システム)に加えて、Webサーバとして附属図書館のホームページを提供しています。CA on CDをはじめとする各種のデータベースや電子ジャーナルなどの電子化された資料を利用したり、文献複写や参考調査の申込みをオンラインで行うことができます。また、インターネット資源のナビゲーションサービスのページの充実や、図書館資料の新着情報の提供などのサービスについても検討しています。
一般にMagazine と Journal は日本語に訳すとどちらも雑誌となりますが、図書館の世界では両者を使い分けております。雑誌のタイトルからこれらを区別することは困難です。例えば、この後で引用します D-Lib Magazine という電子図書館関係の雑誌は、タイトルには Magazine とありますがJournal に区分されます。一つの方法として、広告の分量が比較的多ければ Magazine だろうと判断することもできますが、図書館では、中に盛られている記事内容によって両者を区別しています。
Magazine は、著者の個人的・主観的な調査や観察、意見等の記事からなり、Journal には、科学的・客観的な観察、実験、調査に基づく記事が掲載されております。又、Journal 論文は、引用あるいは参照した基本的かつ重要な先行論文を、参考文献として末尾にあげることになっております。
しかし、一番の相違は、Journal においては投稿された原稿が最終的に雑誌に掲載されるまで、匿名の何人かの査読者による査読と、その結果としての何回かの書き直しを経て、おおよそ3か月〜6か月、場合によっては9か月を要するという、レフェリー制度(ピアレビュー制度)があるという点でしょう。Journal の質は、査読者にも原稿の著者が誰であるかわからないようにするダブルブラインド原則を採用するなど、その編集者による査読過程統制の厳格さによって判断され、そのような雑誌に掲載されたことが、論文の学問的水準の高さを保証することにもなります。
"Publish or perish" の米国では、研究者達は、いかに速く、いかに多くの雑誌に論文が掲載されるかについて腐心しているようです。没にならずに首尾よく採択されて掲載の運びとなるのは、論文を書くより難しく、いかに編集者・査読者にアピールするかについて、あの手この手の指南 (Christopher Edwards, "Publishers roulette : Beating the odds." http://freon.chem.swin.edu.au/~marg/adapt.html )が数多くあることもPeer-review の厳しさを物語っています。
Peer-review であることが掲載論文の学問的有用性の保証になるということは、電子図書館と電子ジャーナルについて考える時に重要になります。大手出版社の電子ジャーナルは冊子体との抱き合わせで高額、あるいは国の会計制度と相容れないなどの理由で導入が進みませんが、その一方で冊子体の電子化版ではない、最初から電子媒体のみの電子ジャーナルも増えてきており、それらはフリーアクセスのものが多いようです。
アクセス料金については、少なくとも学会発行の電子ジャーナルについては無料でありうると思いますし、又、そのような論調(Stevan Harnad, "Free at last : The future of peer-reviewed journals" D-Lib Magazine. vol.5, no.12(Dec., 1999) http://www.dlib.org/dlib/december99/12harnad.html )もあります。現に、1995年にスタンフォード大学内に設立された非営利団体 HighWire Press が提供する電子ジャーナルは、二、三のフリーサイトのものを除いては最新巻や最近1年分は読めないなどの制限はありますが、かなりのものが無料になっています。
図書館の電子図書館化施策の一つとして、ホームページに電子ジャーナルへのリンクをはることを多くの図書館で実施しております。しかし、リンクをたどって行き着いた先が有料であったり、登録制であったりして実際には読むことができないのであれば、利用者のフラストレーションがたまるだけです。そこで、現在の状況では、フリーの電子ジャーナルへのリンクを考えることになりますが、今度は逆にJournalの質が心配になります。無料だからと何にでもリンクをはるのも考えものです。「利用者は、質よりも入手しやすい方の情報を選ぶ傾向にある」(Thomas Mann's Principle of Least Effort)そうですから、この傾向を助長することになります。
選定の際には、Peer-review 誌であるかどうかが一つの判断材料になります。下図は、アメリカ癌学会発行のCA : a cancer journal for clinicians のホームページ (http://www.ca-journal.org/home/home.html)の一部ですが、Peer-review 誌であることをうたっています。
※試行版の電子ジャーナル一覧をhttp://www.cc.mie-u.ac.jp/~ez13691/list.htmに置いておりますので興味のある方はご覧ください。
| 資 料 名 | 内 容( 受 入 年 度 ) |
| 大正・昭和期経済統計資料 (マイクロ・フィルム) |
一部明治末期をふくめて大正期から昭和前期にいたる間の経済統計資料(経済一般、金融、物価、賃金、工鉱業、会社、取引所、海運、農林水産、植民地経営等)を網羅する。 収録タイトル:本邦経済統計、金融経済統計、物価統計表、賃金統計表、労働統計要覧、主要工業総覧、会社統計表、取引所一覧、海運概況、製鉄業参考資料、本邦鉱業一趨勢、米統計表、肥料要覧、繭統計表、蚕糸類及真綿統計表、山林要覧、水産年鑑、産業組合要覧、拓務統計。(昭和56年度) |
| 土地経済資料 (マイクロ・フィルム) |
明治期から昭和20年までの間に実施又は刊行された農林省(農商務省)を主とした中央官庁及び地方官公庁、農業団体等による調査・統計書1,060 点余りをマイクロ・フィルム110 リ−ルに収録したものである。 小作調査会議事録、耕地拡張改良事業要覧、山林局統計年報、小作慣行調査、地方小作官会議録、小作(農地)年報、農家経済調査、伊勢の株地制度考、伊勢暴動(明治9年)顛末記等々戦前期日本の土地問題・農業問題・農村社会政策に関する原資料の大部分を収録。(昭和56年度) |
| 連歌俳諧書集成 (マイクロ・フィッシュ) |
東京大学総合図書館の蔵書である洒竹文庫、竹冷文庫、知十文庫のマイクロ・フィッシュ版である。 洒竹文庫は、俳諧の史的研究に力を注いだ俳人、大野洒竹(1872 〜1913) の収集になるもので、東京大学に寄贈された当初は4,000 部だったが、関東大震災で1,000 部が亡失し、このマイクロ・フィッシュ版には、残った3,000 部のうちから2,612 部が収められている。 竹冷文庫は政治家俳人、角田竹冷(1856 〜1919) の収集した1,450 部のうちから550 部、知十文庫は、俳人岡野知十(1860 〜1932) の収集した江戸座を中心にしたもの450 部のうちから235 部が収められている。 主なものに、荒木田守武「守武千句」(天文9年)、谷宗養「天水抄」(永禄4年)、斎藤徳元「徳元千句」(寛永5年)、松江重頼「犬子集」(寛永10年)等がある。(昭和59年度) |
| 水資源関係論文コレクション (マイクロ・フィッシュ) |
米国の地質調査所が1896年から1983年の間に刊行した報告書のうちから地上水、地下水、水質の三部門の水資源関係の論文を集めた"U.S. Geological Survey Water Supply Papers.1896〜1983 "と、Dissertation Abstracts Online からWater Resource, Water Quality, Water Balanceの三つのキ−ワ−ドを使って検索した1978年以降1987年までの米国学位論文 413点の二種類の資料からなる。(昭和62年度) |
| 1985年農業センサス 農業集落カ−ド 全県セット (マイクロ・フィッシュ) |
1985年に行われた農業センサス(全国の農業従事者全員を調査対象にして実施される)の集計結果で、各農業集落単位に、農家総数から始まって専業兼業の別、農家人口、性別、年齢、生産物など、多岐にわたって調査されている。地域毎の農業の構造を調べるうえで、基本的な資料となるもの。(平成元年度) |
| Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. (グメリンハンドブック) |
網羅性においては有機化学分野のバイルシュタインと並び称される無機化学では最大のデータブック。最初の刊行は1817年で内容の更新は補遺版の形でなされている。全71システム中、希ガス、水素、酸素、窒素、塩素、臭素、ヨウ素、硫黄、ホウ素、炭素、珪素、リチウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム、亜鉛、アルミニウム、チタン、バナジウム、クロム、マンガン、ニッケル、コバルト、銅の25システム222冊を購入。(平成7年度) |
| 百部叢書集成 | 宋から清末までの中国で刊行された主要な叢書100部を影印刊行したもので、中国文学、中国語学、中国史、中国美術史、考古学等広く中国学全般にわたり、学術研究上重要な資料を多く含む。 また、四部分類叢書集成としてそれぞれ30部ずつ収録して刊行された、續編・三編を含む。(平成9年度) |