- ホーム
- 研究開発室
- 活動
- ?「発見塾」三重大学シリーズ
- ?「発見塾」2009年度開催記録
?「発見塾」2009年度開催記録
[ ?「発見塾」について | 開催案内 | これまでの開催記録 ]
?「発見塾」のページは2015年度から博学連携推進室に移動しました。
?「発見塾」三重大学シリーズ 2009
開催日 5月23日(土)13:30~15:45 <チラシ>
会 場 津図書館 2F視聴覚室
テーマ 「藤堂高虎の「実像」に迫る」
講 師 山口 泰弘(やまぐち やすひろ) 三重大学教育学部・教授
参加者 73名
藤堂藩の藩祖藤堂高虎(1556~1630)の肖像画は、礼拝の対象として数多く描かれました。 その大半は長い年月のなかで失われましたが、今日わずかに遺る作品のなかには、 近世初期を代表する武家肖像画として重要文化財に指定されているものもあります。 不思議なことに、高虎を描いたといわれる肖像画には、全く容貌の異なる2種の系統があり、 またそれぞれの系統には判を押したように同じ画像の画幅があります。講座では、このふたつの問題を解くことを糸口に高虎の実像に迫り、さらに近世における肖像画の制作の実態を探っていきます。
 |
 |
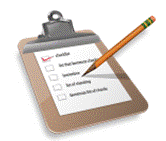 |
< 参加者の声 > ・テーマにふさわしく大変分かりやすかった。 ・歴史的、文化的遺跡を見学しながらの講習なんかも面白いのでは? ・絵画からいろいろな事が読み取れることが分かり、視野が広がった。 |
開催日 7月25日(土)13:00~15:30 <チラシ>
会 場 津図書館 2F視聴覚室
テーマ 「津市の歴史・文化的景観を活かしたまちづくり ―景観法と景観まちづくり―」
講 師 浅野 聡(あさの さとし) 三重大学院工学研究科・准教授
参加者 57名
景観法を知っていますか。同法は2004年に制定された国内初の景観に関する基本法であり、 都市、農村、森林、河川、海岸などと国土であればどこでも対象にすることが出来るのが大きな特徴です。 現在、多くの自治体が景観計画の策定に取り組んでおり、県内では、三重県、松阪市、伊賀市などで既に策定され運用が始まっています。津市も今後策定予定ですが、市内にも伊勢街道を始めとして、津城下町地区や一身田寺内地区など、 多くの歴史・文化的景観を抱えています。地域固有の景観を再評価し、暮らしやすいまちを目指す景観まちづくりの必要性、 直面している景観問題、動き始めた各地の事例、津市における可能性などについてわかりやすく解説します。
 |
 |
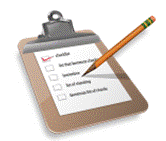 |
< 参加者の声 > ・県都(水と空気のおいしい街)を大切に したい。 ・今回初めての参加ですので、出来れば これからもお話を聞きに参加させて頂き たいと思います。 ・もっと、津城をいかした街づくりをしてほ しいと思いました。 |
開催日 9月26日(土) 13:30~15:30 <チラシ>
会 場 津市美里町 美里文化センター内 「文化ホール」
テーマ 「森の中の「かび」や「きのこ」のお話」
講 師 伊藤 進一郎(いとう しんいちろう) 三重大学院生物資源学研究科・教授
参加者 65名
シイタケはお店でいつでも買えますが、マツタケは買えません。なぜでしょう? 「かび」や「きのこ」は、植物と違って自分で栄養を作れないため、他の生物から 栄養を貰わなければなりません。実は、栄養の取り方が「かび」や「きのこ」の種類で 違います。マツタケはマツの根に共生してマツから栄養を貰い、マツには水分などを与えて 成長を助けています。一方シイタケは、森の中の腐った枯れ木などから栄養をもらっているため 人工培養が可能です。森には多様な「かび」や「きのこ」がいます。普段注目されない、森の 「かび」や「きのこ」を紹介します。
 |
 |
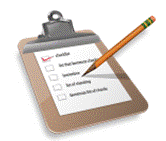 |
< 参加者の声 > ・松茸が沢山できる様になったらいいですね。 ・今まで知らなかった事を教えて頂いたと 思います。 ・たまたま新聞を丁寧に読んだので、今回の 講演会を知りましたが、「発見塾」なるも のは全く知りませんでした。もっと目に 入りやすいようPRしたらいかがですか。 |
開催日 11月28日(土) 13:30~15:30 <チラシ>
会 場 津センターパレス地下 まん中交流館 「研修室」
テーマ 「草陰のアノな行かむと墾(は)りし道」
講 師 廣岡 義隆(ひろおか よしたか) 三重大学人文学部・教授
参加者 49名
『萬葉集』の中に「東歌」と呼ばれる二百首余りの歌があります。そうした中の一首に、
草陰の 安努な行かむと 墾りし道 安努は行かずて 荒草立ちぬ (十四・三四四七)
(くさかげの あのなゆかむと はりしみち あのはゆかずて あらくさだちぬ)
の歌があります。アノと呼ばれる地域を歌ったこの一首の萬葉集について考えます。 話の中では、孝徳天皇による畿内制の成立と、古代における「東」の範囲及び「東歌」の分布について考えると共に、 そもそも「東歌」とは一体何であるのかということについても、皆さんと一緒に考えたいと思います。 郷土と文学の接点からの話になります。
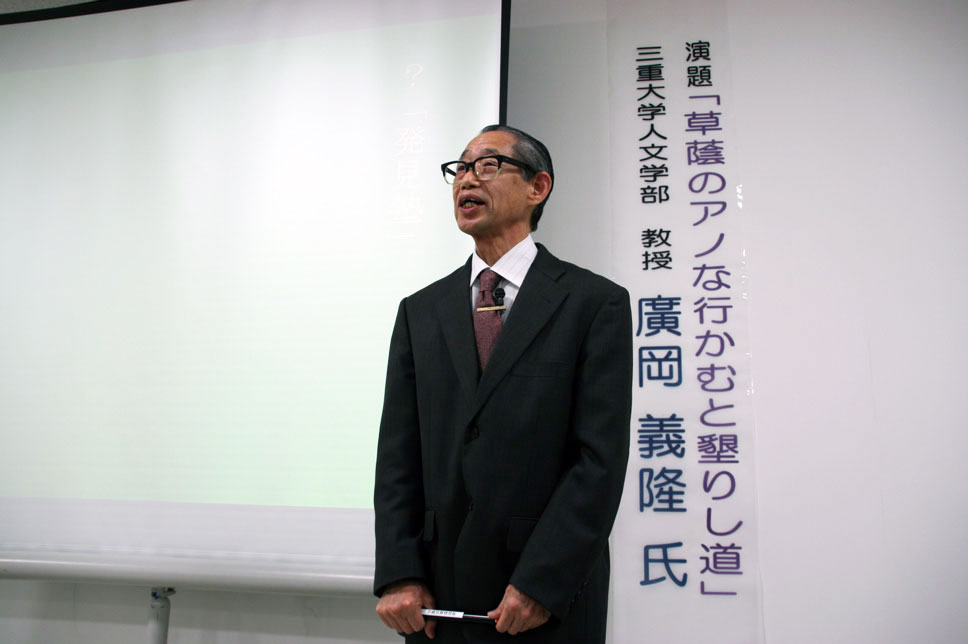 |
 |
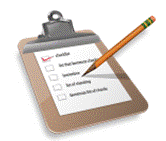 |
< 参加者の声 > ・「発見塾」は数回、大変興味を持って聞きました。これからも継続してください。 ・万葉集の時代の人の思い垣間見られた(理解できた)ようで、少し心豊かになったように感じられました。 |
開催日 1月23日(土) 13:30~15:30 <チラシ>
会 場 津市一志保健センター
テーマ 「認知症を少しでも理解するために」
講 師 成田 有吾(なりた ゆうご) 三重大学医学部・教授
参加者 144名
高齢化に伴い認知症の患者さんがふえています。避けられない老化と密接に関係していますが、今できることについて、是非、皆さんにもお考えいただきたいと思います。 私のお話では、どのようなものを認知症と呼ぶのか、頻度の多い認知症にはどのようなものがあるのか、 アルツハイマー病、前頭側頭葉型認知症、レビー小体型認知症、脳血管性認知症、正常圧水頭症などの病気でよく見られる症状や背景、診断、治療、予防の現状、および患者さんや家族を支える社会の対応について、 1時間ほどお時間をいただく予定です。
 |
 |
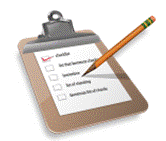 |
< 参加者の声 > ・テーマが良かったと思います。今後もこういう講演を続けて下さい。 ・今後とも一志方面で数多く開催して下さい。津まで出るのは面倒。 |
開催日 3月27日(土) 13:30~15:30 <チラシ>
会 場 津図書館 2F視聴覚室
テーマ 「乗物酔いの科学と技術」
講 師 井須 尚紀(いす なおき) 三重大学院工学研究科・教授
参加者 42名
船や車での乗物酔いを多くの人が経験しています。いわゆる乗り物以外でも、 無重力下で起こる宇宙酔いもよく知られていますし、大画面映画や遊園地のバーチャルリアリティでも乗物酔いが起こります。自動車の運転講習などで使われ るシュミレーターでは、運転経験の多い人ほど酔い易いと言われています。では、人はどうして乗物に乗ると酔うのでしょう。乗物酔いが起こる仕組みや原因を 解説し、乗物酔い対処法について考えます。 また、現在進めている研究の中から、車酔いを軽減する車載ディスプレイの開発研究を紹介します。
 |
 |
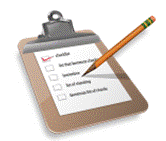 |
< 参加者の声 > ・3D映像などを作成しながら研究されている事など、自分ではとても出来ない事について、紹介して頂きとても面白かったです。車載TVの研究も凄いと思いました。自分も酔いを経験する事があるので、身近なテーマでとても興味深かったです。 ・この様な尊い研究のおかげで生活し易い(社会の進歩に合う)社会が作られていくのだと、改めて感謝の気持ちが湧いた。 |