- ホーム
- 研究開発室
- 活動
- ?「発見塾」三重大学シリーズ
- ?「発見塾」2010年度開催記録
?「発見塾」2010年度開催記録
[ ?「発見塾」について | 開催案内 | これまでの開催記録 ]
?「発見塾」のページは2015年度から博学連携推進室に移動しました。
?「発見塾」三重大学シリーズ 2010
| 開催日 5月22日(土)13:30~15:30 <チラシ> 会 場 津図書館 2階視聴覚室(津リージョンプラザ内) テーマ 「子どもの健康と運動」 講 師 冨樫 健二(とがし けんじ) 三重大学教育学部保健体育科・教授 参加者 35名 少子化や遊びの環境が変わったことにより子どもの運動量が減少し、身体活動量の二極化や低体力化などの問題が顕在化しています。 子どもから大人にかけての発育期に十分な運動刺激がないとからだはどのようになってしまうのでしょうか。われわれは子どもに対し どのような環境を作っていくべきなのでしょうか。本講座では昨今子どもに増えている肥満ややせ、喘息やアレルギーなどの健康課題と 運動との関わりについてわかりやすく解説していきます。
◆ 冨樫健二氏の著作 |
||||
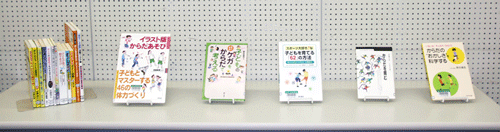 |
◆ トピック
・ 2009年度、?「発見塾」全6回講演をお聞き下さった方への記念品贈答式が
講演終了後行われました。
・ 会場内後方に、テーマに沿った書籍が陳列されました。
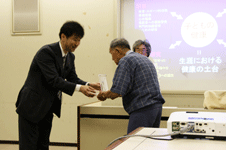 |
 |
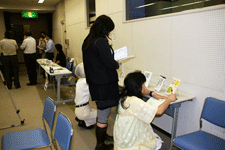 |
 |
開催日 7月24日(土)13:30~15:30 <チラシ>
会 場 津図書館2階 視聴覚室(津リージョンプラザ内)
テーマ 「最近の海の環境問題と私たちの生活」
講 師 前田 広人(まえだ ひろと) 三重大学生物資源学研究科・教授
参加者 30名
最近、地球温暖化に伴う海水温の上昇が頻繁に取り沙汰されるようになりました。僅か1℃の水温の上昇でも、 さまざまな水域でこれまでにない異常な現象が報告されています。例えば、磯焼けやサンゴの白化現象などが その端的な例です。そして、このような環境の異変は、最終的には水産資源の枯渇につながるのではないかと 危惧されています。今回は以下の課題について紹介します。
1.閉鎖性水域の富栄養化
2.地球温暖化に伴う陸水および海水温上昇
3.水産養殖とゼロエミッション化
4.地下水の硝酸塩濃度の上昇
5.食糧生産と水
 |
 |
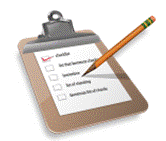 |
< 参加者の声 > ・伊勢湾の汚染対策の現状をもっと知りたかった。 ・講演会は出来る限り土・日にお願いします。参加しやすいため。 |
◆ 前田広人氏の業績等
* 「海洋環境アセスメントのための微生物実験法」 恒星社厚生閣(2000)
* 「増補改訂版 世界の湖」 人文書院(2001)
* 「海の環境微生物学」 恒星社厚生閣(2005)
* 「薬剤による赤潮駆除技術」 日本水産学会誌(2008)
◆ 津市図書館で借りられる本 (下記画像をクリックすると詳細がご覧いただけます。)
 |
開催日 9月25日(土)13:30~15:30 <チラシ>
会 場 久居中央公民館3F 大会議室
テーマ 「からだにやさしい発酵食品」
講 師 磯部 由香(いそべ ゆか) 三重大学教育学部・准教授
参加者 66名
人は、昔からさまざまな発酵食品を作り出してきました。これまで、発酵食品は食品の保存性を高め、 元の食品にはない独特の風味を持つことで、私たちの食生活を豊かにしてきてくれました。これに加えて、 最近では、発酵食品の中に、私たちの健康を支えてくれるさまざまな成分が含まれていることが明らかに なってきました。今回は、具体的な発酵食品を取り上げ、最近の研究成果をふまえて、健康への有用性 について解説します。
 |
 |
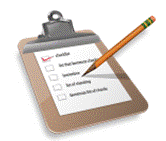 |
< 参加者の声 > ・わかりやすく楽しいお話でした。有難うございました。 ・大変有意義でした。先生の熱意に感動です。これからも三重県の産業の為に御尽力下さい。 ・血圧が高い私はGABA入りの食品を食べようかと思います。今も納豆は食べていますが。今日教えて貰ったので、あらためていい食品なのでしっかりと食べようと思います。 |
◆ 磯部由香氏の業績等
* 「あまご麹漬けに及ぼす本漬け期間および茶添加の影響」共著
三重大学教育学部研究紀要(2010)
* 「ふなずしの微生物相」共著 日本家政学会(2002)
* 「食生活論」共著 朝倉書店(2007)
* 「食の視点」共著 文理閣(2009)
開催日 11月27日(土)13:30~15:30 <チラシ>
会 場 津市まん中交流館 研修室(津センターパレス地下)
テーマ 「音環境とサウンドスケープ」
講 師 寺島 貴根(てらしま たかね) 三重大学工学研究科・准教授
参加者 28名
地球環境が大きな話題となっている今日において忘れがちですが、音は身近で大切な環境の一つです。 私たちのまわりには様々な音が存在し、取り除きたい騒音もあれば、心に残る美しい音色もあり、 風景と同じように我々の生活空間を形作っているのです。そして音のひとつひとつには存在理由があり意味があります。 この講演では、音の文化的背景を明らかにしようとするサウンドスケープの考え方を紹介し、快適な音環境について いっしょに考えていきます。
 |
 |
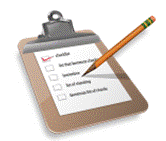 |
< 参加者の声 > ・今年から受講を始めましたが、私には真に発見で、良いテーマばかりです。主催の方に感謝します。 ・後半から事例が増えてわかりやすくなり、おもしろいなと感じました。もっといろんな音や事例を紹介して欲しいなと思いました。津市の音を再発見によって、津市をもっと好きになるのではと思いました。 |
◆ 寺島貴根氏の業績等
* 「ステージ上の音響条件に対する指揮者と演奏者の主観の差異」共著
日本建築学会環境系論文集654(2010年)
* 「伊勢神宮(内宮)の音環境調査」
日本音響学会騒音・振動研究会資料(2009)N-2009-35
* 「波音の保全・導入による海浜地域の音環境整備、騒音制御」
日本騒音制御工学会誌(2008)Vol.32
* 三重県環境影響評価委員会委員・三重県公害審査会委員
開催日 1月22日(土)13:30~15:30 <チラシ>
会 場 津市白山総合文化センター 多目的室
テーマ 「目からウロコ! 背骨の病気の大発見」
講 師 笠井 裕一(かさい ゆういち) 三重大学大学院医学系研究科 脊椎外科・医用工学・教授
参加者 100名
私は15年間で3000人以上の背骨の病気の患者さんの手術を担当してきました。その中で、患者さんから多くのヒントをいただき、さまざまな発見をしま した。一例を紹介しますが、首の手術をした患者さんの目を診ているうちにヒントを得て、「首の神経の通る管が狭い人は、左右の目の間の距離が短い」という ことを見つけました。今回の講演では、「ヘェーそうなの?」と思える発見トリビアを15個選んで、それらを面白くわかりやすく解説したいと思います。
 |
 |
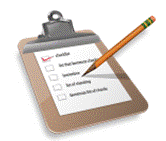 |
< 参加者の声 > ・発見15。面白く興味が持てた。自分で簡単に見つける方法を教えて貰ってよかった。 ・非常に感動のある講演で、内容を友人・知人に伝えたいと思いました。具体的な話でしたから高齢者にもよく理解できました。 |
◆ 笠井裕一氏の業績等
* 「整形外科ナースのための疾患別ケアハンドブック」 メディカ出版
* 筆頭著者として、英文約 50編、和文約 120編あり。
* 日本脊椎脊髄病学会評議員・日本運動器疼痛研究会理事など。
開催日 3月19日(土)13:30~15:30 <チラシ>
会 場 津リージョンプラザ2階 健康教室
テーマ 「江戸時代の伊勢参り -津を通った弥次さん喜多さん-」
講 師 吉丸 雄哉(よしまる かつや) 三重大学人文学部・准教授
参加者 95名
『道中膝栗毛』でおなじみの弥次さん喜多さんの旅は、伊勢参りが目的でした。『東海道中膝栗毛』五編上・下・追加には、 桑名から津を通って伊勢に参宮する様子が描かれています。津をはじめとする伊勢街道の町々は、弥次さん喜多さんの目に、 どのように映ったのでしょうか。『東海道中膝栗毛』のほか、同じく十返舎一九の手になる案内記『金草鞋』や当時の代表的な 地誌『伊勢参宮名所図会』など、江戸時代の史料を手がかりに、往時の伊勢参りを追体験いたしましょう。
 |
 |
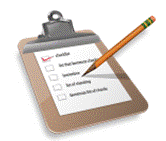 |
< 参加者の声 > ・初めて聞かせて頂き有難うございました。又勉強させて下さい。 ・いつどこで何があるかわからないので、もっと新聞とかで告知して下さい。 |
◆ 吉丸雄哉氏のプロフィール・業績等
* 昭和48年 長崎県に生まれる。
* 平成16年 東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。
* 平成19年 「式亭三馬の研究」により、博士(文学)取得。
* 平成23年4月より、三重大学人文学部准教授。
* 専攻は日本近世文学。
著書に「大学生のためのワークブック 江戸の詩歌と小説を知る本」共著
「武器で読む八犬伝」単著等

